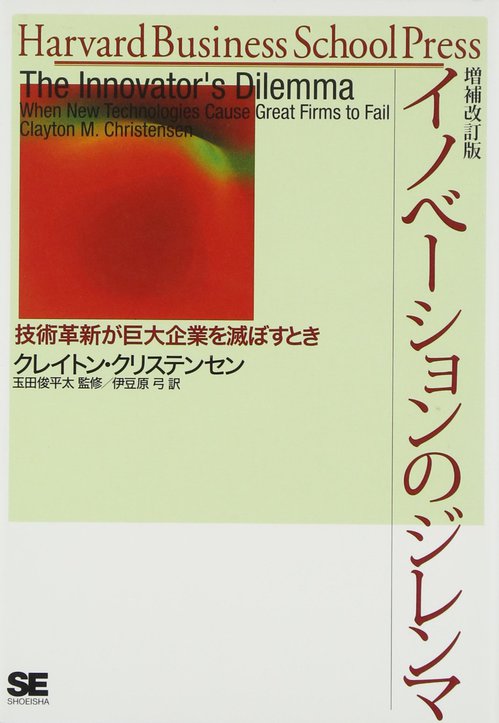【〜逆張りのススメ〜競争優位を獲得する SOCO/AO/SUNが3年で3店舗出店できた理由 その2】
前回の続きです。
【前回のまとめ】
1 逆張りについて
2 競争優位について
3 SOCO/AO/SUNが3年で3店舗を出せた理由は、他サロンが
「やりたくてもできないこと」
「やりたがらないこと」
「まねされにくいこと」
をやってきたから。
前回は上記3点について書きました
【本記事で理解できること】
1 ヘアサロン経営の参考になる
2 SOCO/AO/SUNがオープンからやってきた取り組みがわかる
3 競争優位を獲得するための具体的方法がわかる
では、前回最後にお伝えした
SOCO/AO/SUNが競争優位を獲得するためにやってきた詳細について解説します。
《他サロンがやりたくてもできないこと》
突っ込んだクリエイティブコンテンツ×マーケティング視点
《他サロンがやりたがらないこと》
「クリエイティブ系」×「ネット広告」×「低単価」
《他サロンにまねされにくいこと》
美容室経営 × マネジメント
美容室経営 × マーケティング
美容室経営 × アナリティクス
美容室経営 × リクルーティング
以上が、我々のやってきた競争優位を獲得するための取り組みでした。
以下、詳細を述べますが、内容が前回より少し難しくなります。
しかし、理解できれば美容室経営で起こっている現在進行形の重要なことが見えてきます。
1.【他サロンがやりたくてもできないこと】
〜突っ込んだクリエイティブコンテンツ×マーケティング視点〜
僕のブログを読んでいる方の中には「文は長いし難しい言葉も出てくるし、、」で、
合理的なビジネスマンのように感じる方がいるかもしれません。
ですが、元々はクリエイティブ大好きサブカルクソ野郎でした。
クリエイティブなことや創作することが好きだったので美容師になりました。
HPのデザイン、内装デザイン、名刺デザインなど、デザインに関する領域全般や、写真撮影、加工、音楽・映像制作もやります。
ウチのHPを見るとわかるかと思いますが、人によっては「なんだコレ」と思うでしょう。
通常、マーケティング視点で考えると、こういったHPを作ってはいけません。
日本では写真より文字情報の方が強いからです。
なぜ日本において文字情報の方が強いのかの理由に関しては ダサい?『洋画ポスターの日本版』にツッコみが入りまくってる件 をみるとわかりやすいかもしれません。
世にある多くのHPは、文字が多く、ワンカラム(例)1ページで縦長の、情報量が多く誰にでもわかりやすいHP)で見やすく作くられています。
逆に、SOCO/AO/SUNのHPは、写真が全面に出るようにデザインされています。
そして、他サロンよりクリエイティブ色が色濃く出るよう意図しています。
一方で、ウチのホットペッパーやminimoのレイアウトは明確なマーケティング視点です。
文字で埋めて、わかりやすい構成になるよう心がけ、顧客が何を求めているかを最優先に考えて設計しています。
理由としては
HP・インスタ→「人事視点」
ホットペッパー・minimo→「集客視点」
と完全に分けて考えているからです。
ここが【他サロンがやりたくてもできないこと】のポイントの一つです。
通常のサロン、特にクリエイティブ系のサロンは、世界観を統一させるために、もしくは雛形どおりのブランディング視点しかないために、どの媒体であっても、同じようなコンテンツ・世界観の扱い方をします。
しかし、そうすると、興味を持ってもらえる層が限定されていきます。
いえ、その方向は正しいのですが、突出したブランドを構築できる一部のサロン以外は差別化することが難しい。埋没してしまうのです。
特にクリエイティブ推しのサロンは、ブランディングに固執するあまり、マーケットの裾野を狭く考えてしまっている。
自分たちが想像している以上に、世の中には潜在顧客がたくさんいます。
逆にクリエイティブ系サロンの強みは美容師、美容学生からの支持が厚いことです。
経営視点で業績は伸びていないのに、美容師・美容学生からの人気が高いサロンがあります。
「ブランドサロン」と呼ばれるところの一部です。
逆に市場で成功している大手美容室は常に人材難で苦労している。
高いお金をかけて求人広告を打ってもなかなか効果が出ない。
大学生の就活市場では大企業に入りたいという層がマジョリティですが、我々の業界ではマイノリティです。
人事において我々の業界は特殊な業界なのです。
「大きい会社」=「入りたい会社」
という認識では成り立っていません。
それよりも、イケてる美容室、オシャレでカッコいい美容室に人気が集まる傾向があります。
そういった業界の「ねじれ」に競争優位を見出すヒントがあります。
人材市場で人気があるのに、ビジネスベースでは成功していない。
コレは不思議なことです。
逆に考えると、両方を成立させることができれば競争優位を獲得できるだろうと判断しました。
なぜなら「他のサロンがやりたくてもできないこと」だからです。
そこで我々は、結果を出すためにねじれ構造を意図的に狙って、マーケットベースでも、人事ベースでもあえてブランディングの方向性を限定せず、他とは違うやり方で成果を狙いにいきました。
その時武器としたのが、元々持っていたクリエイティビティとマーケティングの視点です。
突き抜けたクリエイティブをやりながら人事を動かしつつ、ネット広告などをマーケティング視点で攻略し、売上を最短で伸ばすこと。
これが「他がサロンがやりたくてもできないこと」です。
そうしないと3年で3店舗というスピードは不可能です。
このパートの最後に「やりたくてもできないこと」に成功している顕著な例を挙げましょう。
具体名を出してしまいますが「Album」さんは低単価サロンのセグメントで、あれだけ質の高いコンテンツを成立させています。
さらにインスタのフォロワー数十万と、メディア化にも成功している
なかなかやりたくても真似できないでしょう。
みなさんご存知のように市場を席巻していった。
経営視点を用いて業界を「出し抜いた」模範的な例です。
2.【他サロンがやりたがらないこと】
〜「クリエイティブ系」×「ネット広告」×「低単価」〜
続いて「他サロンがやりたがらないこと」についてお伝えします。
これを語るには、創業から今まで我々が取り組んできたネット広告における施策をお伝えするのがわかりやすいでしょう。
我々は創業当初からネット広告への掲載を積極的に行ってきました。
美容業界をざっくり二つに分けると「コンサバ系」と「クリエイティブ系」に分けられます。昔は赤文字系、青文字系とも言われていました。
SOCOは二つの属性の中では「クリエイティブ系」のお店としてスタートしました。
当時「クリエイティブ系」のお店は総じてネット広告媒体への参画に消極的でした。
「コンサバ系」のネット広告市場はすでに成熟しつつありましたが「クリエイティブ系」の市場はまだ成熟しきっていなかったのです。差別化を図れる領域が残されていました。
具体的にどの領域で差別化を図れたのかというと「プライス設定」です。
クリエイティブ系のサロンでホットペッパーを打っているところは当時からたくさんありましたが、大きく下げて掲載しているところはあまりありませんでした。
下げても通常プライスの10%オフくらい。もしくは通常プライスにトリートメントサービスくらいでした。
そこで我々は、通常プライスに対して30%オフで攻め込むことにしました。
またプロパー(正規の値段)のプライスも同エリア・同ポジションのサロンがカット6480円平均のところを5400円に設定しました。
カラーや他メニューのプライスも同じように他社よりお手頃な価格設定としました。
同時に、リピートを促す施策を開始しました。
来店後、顧客に対して個別でDMを送信。さらに2週間後に自動DMが送られるよう設定し、1回目の来店後は20%オフ、2回目の来店後は10%オフ、3ヶ月再来がない場合は再度10%オフのDMが自動で送られる仕組みを構築しました。
今ではどこのサロンでも再来を促す施策を打っているかと思いますが、当時は自動DMの使い方などの知識がそこまで認知されていなく、差別化できる領域でした。
この施策によって、リピートが増え、徐々に業績を伸ばすことができました。これが1年目。
2年目には「minimoの集客力が強い」という情報を得て、積極的に取り組むようにしました。
minimoに関しては創業直後からアカウントを作って試してはいたのですが、まったく反応がなく放置していました。
minimo内部には「人気順」という仕組みがあって、人気順上位に表示されると、かなり集客できるということがわかりました。
そこで、それまでやっていた楽天ビューティーやその他効果の出ない予約導線アプリを全て掲載停止し、全リソースをminimoに注ぐことにしました。
取り組み始めて最初にやったことはminimoの内部分析です。
どうしたら人気順の変動が起こるか分析し、有効な手段を発見するたびに全体ラインでシェアして有効施策を実施するよう指示・監督しました。
その結果、売上は大きく伸び2店舗目であるAO出店に繋がりました。これが2年目。
3年目は上記施策を継続して打ち続け、業績も順調に伸びていきました。
そしてSUN出店という流れになるのですが、そこで一度コケました。
それまで順調に推移していたminimoの人気順が保てなり、大きく下がってしまった。
これにより売上の伸びが鈍化し、頭打ちとなりました。
状況を打開するために再びminimoの分析を掘り下げて再開。
1時間ごとの順位変動やPV変動をエクセルで管理し、どういった要因で順位が動いているのかを細かく分析しました。またその具体的施策を全体でシェアし、指示・監督しました。
結果、順位は再び回復。再び上昇基調に乗りました。これが3年目。
ざっくりネット広告施策における3年間の流れを述べるとこういった感じです。
「値段を下げることなんか簡単じゃん」「そりゃ集客できるだろ」と言われそうですが、そう簡単ではありません。
なぜそこに大きな競争優位性が発生するのか?なぜ他が追随できないのか?
業界が抱えているジレンマがあります。
【なぜプライスを下げることができないのか?ジレンマを突くこと】
クーポンなどを使ってプライスを下げることができないのは、単純に
「利幅が下がるから嫌だ」「美容師的プライドから嫌だ」「価格競争に巻き込まれたくない」というだけの問題でもありません。
実はもっと深いジレンマがあります。
それは「プライスを下げることで既存顧客へのエンゲージメントを毀損するリスクがある」ということです。
エンゲージメントとは顧客との「結びつき」や「信頼」のことです。
プライスを下げることで、昔から正規の値段で継続的に通ってくれているロイヤリティ(忠誠心)の高い顧客への結びつきや信頼を毀損する可能性があるのです。
既存顧客は通常の価格で通っているにも関わらず、隣にはクーポンを使って安い価格できているお客様がいるわけです。
既存顧客は憤慨するかもしれません「私は安売りサロンなどにいきたいわけじゃないのよ」と。
しかし時代の波がクーポンかつ低単価である以上、同じ土俵で戦わないと広いチャネルからの集客は難しい。
ここに「上層部」と「若手スタイリスト」との溝が生まれます。
すでに「雑誌時代」に積み上げてきた顧客がたくさんいる上層部は問題ありません。
ですが、ネット広告を使わないと、若手スタイリストの売り上げを伸ばすことができない。
なぜなら、ホットペッパービューティーやminimoなどを使っているメイン層は、若年層だからです。
むしろネット予約導線は若年層の美容室予約インフラとなっているとすら言える。
若手スタイリストが売り上げを伸ばすためには、同年代のお客様の方がリピート率は高いでしょう。
若手の売り上げを伸ばすためのメイン顧客層が、ホットペッパーやminimoを使っている以上、そこにアプローチしないと、集客し、若手の売り上げを伸ばすことは難しい。
・上の世代はすでに顧客がいてその先の伸びしろは少ない。
・若手は伸びしろがあるのに顧客がつかない。というかつける手段がない。
・若手スタイリストの売り上げを伸ばさないと店舗全体の売上も伸びるわけがない。
・しかし、自身の既存顧客へのエンゲージメントを傷つけたくない上層部・経営者。
コチラを立てればアチラが立たない。
こういったサイクルです。
ここに大きなジレンマがあります。
だからそう簡単にプライスを下げることができない=やりたがらない。という構造になります。
こういった構造的問題点を「カニバリゼーション」(共食い)と言います。
詳細は以前紹介した「イノベーションのジレンマ」に詳しい。
なぜ新興企業が大企業を滅ぼすのか?
なぜ新しい美容室がブランドサロンを駆逐できるのか?
この本を読むと上記のような構造的ジレンマを理解することができます。
低単価に向かうことが業界破壊に繋がるという議論がありますが、まったくの見当違いです。
証拠に、ネット広告、クーポン全盛時代でも高単価でお客さんがたくさん来るサロンは存在します。
値段とそれに見合った価値というのは消費者が決めることです。
業界破壊が進んだのではなく、封建的だった美容業界に消費者の選択肢が広がった。と考える方が正しい。
業界破壊を嘆くのではなく、経営者は広がった選択肢に対してどうアプローチできるのかを考えるべきです。
必要なのは顧客視点で考えることであり、重要なのはどのセグメントで戦うのかの明確な経営判断です。
さて、ざっと僕の考えを述べてきました。
他にも語るべきトピックは山ほどありますが、例によって長くなるので別の機会に。
上記述べた通り、業界の構造、特に雑誌時代に顧客を獲得した美容師がオーナー、かつ現役でバリバリ働いていること。ここに複雑なジレンマがあり、クリエイティブ系の領域では顕著にその傾向が表れていた。ということです。
以上が市場の流れを無視してネット広告やプライス変動などを「やりたがらない」理由の正体であり、我々は他が追随できないことがわかっていたので、その隙を突いて業績を伸ばしてきました。
【他サロンにまねされにくいこと】
さて、最後に「他サロンにマネされにくいこと」について書いていきます。
随分本文が長くなってしまったので、サラッと書きます。
美容室経営 × マネジメント
美容室経営 × マーケティング
美容室経営 × アナリティクス
美容室経営 × リクルーティング
上記4点を挙げました。
実は上記4点の下に無数の組み合わせのテーマが並んでいます。
美容室は全国に24万件あるということは前回のブログに書きました。
24万件ある中で
「マネジメント視点」で経営しているところはどれだけあるでしょうか?
「マーケティング視点」で経営しているところはどれだけあるでしょうか?
ここまで読んだ方はわかるかと思います。
我々の業界ではマネジメント、マーケティングなど、知識やビジネス上のフォーマットを用いてヘアサロンを経営しているところがあまり多くないのです。
これが「マネされにくいこと」です。
僕が「学習が大切」だと述べている本質はここにあります。
競争優位を獲得したいなら学習するのが一番早い。
学習し、基礎的なビジネス上の構造を理解すること。
これがマネされにくい状態を作る第一歩です。
人間の脳内というのは誰にもマネできません。
まずは本などを読んでみて、あぁなるほど、そういうことか。と、情報をインプットすることが重要。
さらに重要なのが学んだ知識を実際の現場に落とし込んでアウトプットすること。
実際に現場にフィードバックすると様々な経験を得ることができます。
アウトプットすることはインプットすることよりさらに難易度が高くなります。
実践で失敗しながら学ぶことで、辛いことや大変なことがたくさん出てきます。
しかし、そのプロセスで得たことは。己の血肉となり、マネされにくいこととなります。
【まとめ】
以上、競争優位を獲得するためには
《他サロンがやりたくてもできないこと》
《他サロンがやりたがらないこと》
《他サロンにまねされにくいこと》
をすることが重要である。
という主張と、それについて今まで我々が行ってきた施策詳細でした。
最後のパートはやや精神論的論考になってしまい申し訳ありません。
本文の長さを考えると今回はこれくらいに。
関山