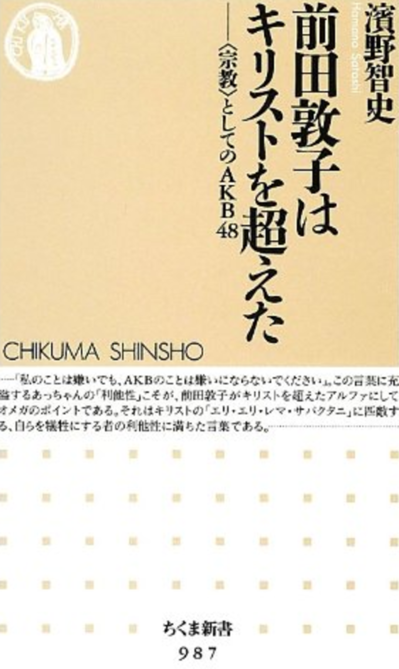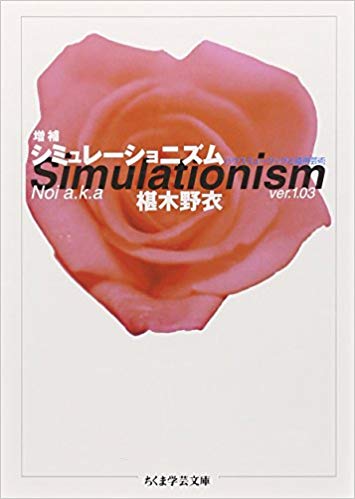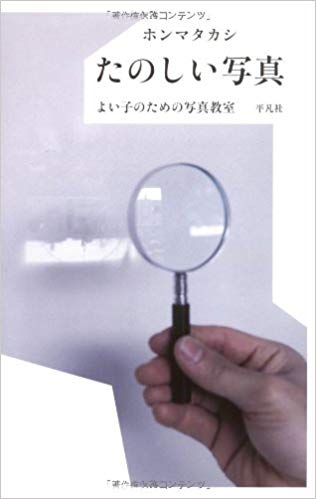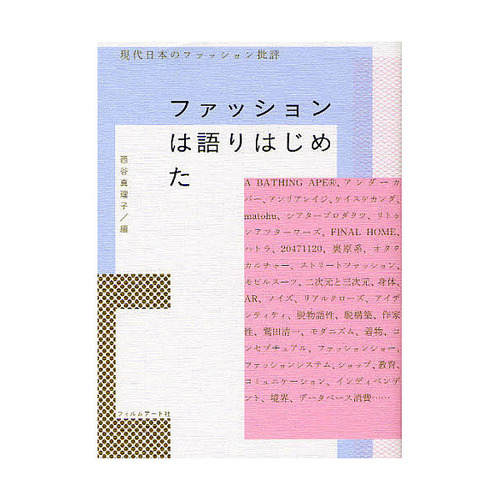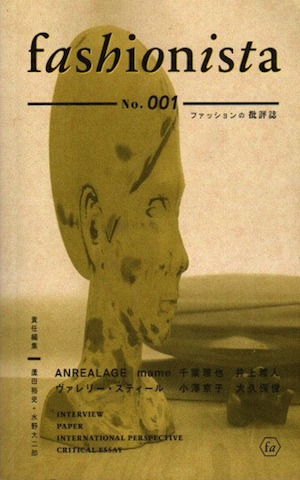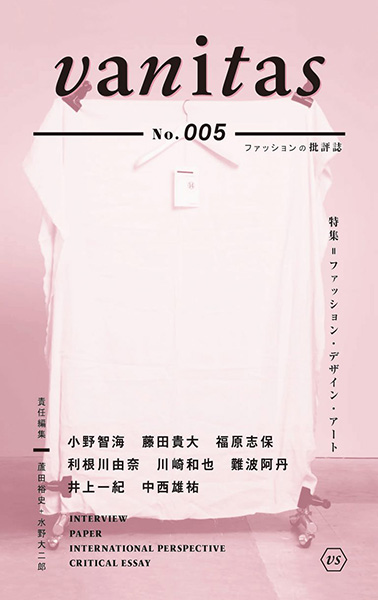【デザイン・アイデアソース公開】 〜5.批評・美術史編〜
さて、長いこと書いてきた「デザイン・アイデアソース公開シリーズ」
長かった。。
今回で最終回。
5.批評・美術史編です。
【アイデアの源泉】
今回の連載中、たびたび「批評」について書いてきました。
デザインにまつわるアイデアソースは世の中にいっぱい転がっています。
しかし、ただ真似るだけだと、言い方悪くいうと「パクる」ことになってしまいます。
まず結論から言うと
すでに全く新しいデザインやコンテンツは存在しない
と考えた方がいいです。
世のデザインで「新しい」と思っても、何かしらの影響を受けたり、すでに誰かがやっていたり。
ヘアデザインでも服のデザインでも「何年代の何風にインスピレーションを受けて」みたいな捉え方をすることが多いと思います。
さらにヘアデザインでは基本的に素材は髪の毛に限定されるので、今までデザインされてきたもの以外で、まったく新しいカタチが存在する可能性は限りなく低いでしょう。
そうすると、「新しそう」に見えるデザインを創作ために、組み合わせたり、何かからインスピレーションを受けて生み出す必要があります。
組み合わせ。DJの仕事に近いかもしれません。
実際にヒップホップでは「サンプリング」といって、ベースのメロディラインを別の音源から引っ張ってきて、それにラップを乗せるという創作方法があります。
《A BATHING APE》のNIGOもヒップホップの文脈に則って、デザインサンプリングした服を作って90年代に大成功しました。
【批評と創作】
NIGOはヒップホップの文脈をうまく使って服作りに転換しました。
組み合わせを変えて物事を捉えるために有効なのが「批評的」考え方です。
実際、僕の経験から最も創作や意思決定に役立ったのが批評的視点でした。
批評的視点で捉えることができるようになれば、例えば先ほどNIGOの成功例で述べたように
ヒップホップの隣にアパレルを成立させることもできます。
極端な例で言えば、EXILEの隣にミケランジェロを置いて捉えることができるかもしれない。
浜崎あゆみの隣にレオナルドダヴィンチを置くこともできるかもしれない。
批評家の濱野智史氏は「前田敦子はキリストを超えた」という書籍を書いています。
(当時結構炎上してました。僕は読んでいないので内容に関して把握していませんが)
このように、前田敦子の隣にキリストを置いて考えてみてもいいのです。
ただデザインソースを見て「かっこいいなー」「おしゃれだなー」
で「真似しよう」だと仮に「パクリだ」と叩かれた時に危うい。
どのような意図があって創作したのか?
自分の創作意図について、文脈を理解しているのか?
批評的視点で考えているのか?
こういったことを知っているか否かの差はデザイン・創作するうえで大きいです。
【オススメの批評文献】
さて本題。オススメの批評文を紹介します。
たくさん挙げると長くなるので、僕が影響を受けた中でもわかりやすく役に立ったな。と思う3作品だけご紹介します。
1.椹木野衣 「シミュレーショニズム」
2.ホンマタカシ 「たのしい写真−よい子のための写真教室」
3.蘆田裕史 千葉雅也 他 「ファッションは語りはじめた」
1.椹木野衣 「シミュレーショニズム」
美術批評家、椹木野衣氏の著書。
「シミュレーショニズム」とは80年代のニューヨークで始まったアート運動のことです。
先ほど述べたサンプリングや、カットアップ、リミックスなどを使って作品を「盗用(パクる)」することがどのような文脈で扱われてきたのか。
美術史的な文脈を絡めて書かれています。
以下引用
「サンプリングに関して認識論的に言及すべき最大の問題は、それが引用ではないという
ことに尽きる。...それはあくまで略奪的な戦略なのであり、『引用』がそれをなす当事
者の表現的自我を不可避的に肥大させるのに対して、サンプリングを敢行した当事者の
自我は抹消され、無名性のなかに雲散する。さらにいえば、引用する者が富めるものから
『収奪』するものを、サンプリングする者は『没収』しているのである。」(248〜9頁)
なるほど。
これの本を読めば、何かに影響を受けて創作する時に、堂々と「パクった」と言えるようになります笑
というよりパクったと言わずにサンプリングしたとかオマージュであるとか、パロディであるとか、別の言い方で理論的骨格を持たせることができるようになるでしょう。
すでに「まったく新しい表現手法が存在しない」と述べました。
そうすると、重要なのは「別の見方で」創作できるようになること。
自分の創作物に自覚的でありたい人は読んでみることをオススメします。
2.ホンマタカシ 「たのしい写真−よい子のための写真教室」
こちら写真家のホンマタカシさんが書いた、写真批評の書籍。
タイトルの通り、平易な文章で、わかりやすく写真について書かれています。
AO代表の松尾がアシスタント時代「写真を撮りたい」となった時に
この本を渡して「写真について勉強しておくように」と言ったことを覚えています。
(その後この本は見当たらなくなった)
3.「写真イメージ編」で少し言及しましたが、「報道写真」や「ニューカラー」についてもこちらの本を読めば写真史の文脈で理解できます。
ホンマさんは今ではファッションフォトは撮っていませんが(たぶん)
昔はCUTiEやZipper(今は共に休刊)などでファッションフォトも撮っていた方です。
写真についての批評文は大変難しいものが多く、なかなかとっつきにくいのですが、こちらの本はそんなことはありません。
手軽に写真批評・写真史について知りたい方は読んでみることをオススメします。
この本を読んで、さらに写真について興味を持った方は
ロラン・バルト「明るい部屋−写真についての覚書」や
スーザン・ソンタグ「写真論」
を読むといいでしょう。
3.蘆田裕史 千葉雅也 他 「ファッションは語りはじめた」
日本のファッションについて分析されているファッション批評の本です。
NIGO、UNDERCOVER、ANREALAGEなど、多くの人が知っているデザイナーやブランドが批評対象として出てきます。
実は日本におけるファッション批評文というのはあまり数がありません。
本著に寄稿している著者達は、全部で11人。
それぞれの視点でファッションについて横断的に述べています。
蘆田さんは他にも
「fashionista」
「vanitas」
などのファッション批評誌を発行されている方です。
現在進行形のファッション批評を知りたい方はまず上記の本からスタートするとわかりやすいかもしれません。
【まとめ】
以上、5.【批評・美術史】でした。
長々と書きながら、多くの人にとってはどうでもいいことを書いてきたしまったような気がして少し後悔しています笑
とはいえ、僕にとっては大変重要なことです。
今まで述べてきたことは、自分の考えの骨格になっています。
独立してから外部の人たちと会ったり話したりする機会が増えました。
その中で、お互いが話す言葉というのは大変重要で、少し話すと相手がどれくらい教養があって、普段どれくらい勉強しているのかはすぐにわかります。
今まで会った人の中で「この人すごいな」「話していて面白いな」と思う人は、もれなく幅広い分野への造詣が深い。
他と違う視点で見たり語ったりしたければ
みんなが「理解不能・どうでもいい」と思っているような、難解な知財に触れてみることです。
幅広い領域を知ることが教養に繋がります。
教養というものは、みんなが「どうでもいい」と思うことについて、真剣にこねくり回すことを中長期的にやってきて、結果として莫大な知性を乗算的に獲得できる素養のことです。
この連載で書いてきたことが、読んでくださった方の何らかの役に立つのであれば幸いです。
最後にフィッツジェラルドの言葉で締めたいと思います。
「第一流の知性とは、二つの相反する考え方を同時に抱きながら、なおかつ思考を機能させる能力を持つことである」
関山
ブログの更新はインスタグラムのストーリーで告知しています。
↓
その他、お店の詳細や求人情報などもこちらが一番早いです。
ぜひフォローよろしくお願いいたします!