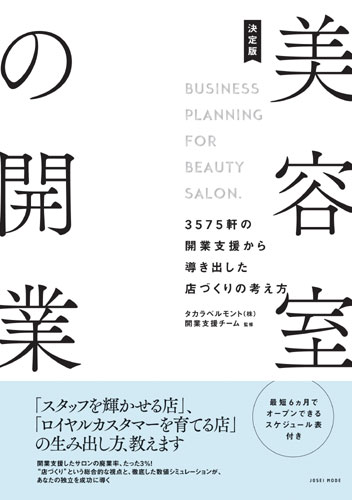あけましておめでとうございます。1年の計は元旦にあり〜正月に考えたこと〜
あけましておめでとうございます。
関山です。
SOCO/AO/SUN 明日から2020年の営業スタートです!
おかげさまで去年は結果を残すことができました。
しかし、去年はもう過去のもの。今年はどうかわからない。
明日からまた、スタッフ一人一人が自分の可能性に挑戦する新たな戦いが始まります。
さらなる飛躍を誓い、頑張って参ります。
今年もたくさんのお客様のヘアチェンジに関われることを楽しみにしております。
本年もよろしくお願いいたします。
さて、新年一発目のブログ。
一発目からクソめんどくさくて超長いんですよ。申し訳ありません。
ほとんどの人にとってはどうでもいい話だと思います。
新年の挨拶だけでお腹いっぱいという方はここでそっ閉じください。
【寝正月】
今年の正月はほぼ寝正月。
ベットに横になりながらネットフリックスを観まくってました。
主にアメリカのビジネス・政治関係のドキュメンタリーを観ました。
あと、少しだけ本も読みました。
その中の一冊「美容室の開業」
素晴らしい一冊です。
美容室の開業関係では稀に見る良著なので、今後独立を考えている美容師さんは読むことをオススメします。
さすがタカラベルモントさん、ちゃんとデータに基づき論理的にわかりやすく構成されています。
・美容室がなぜコモディティに陥っているのか。
・クーポンサイトに頼らない集客設計とは?
・ロイヤルカスタマーを獲得しよう
・今後の美容室新規開業数と競合環境
・美容室は労働集約型ビジネスだから生産性が低い
・資金調達の方法
・財務諸表の基本的な読み方
などなど。
独立後に読んでもかなり勉強になります。
これ一冊をちゃんと理解できれば、出店まで問題なくたどり着くことができるでしょう。
それどころか、隅々までちゃんと勉強することで、他の美容室との差別化を図るためのアイデアが湧いてくるはずです。
素晴らしい本であるのですが、しかし。
ここから先、ちょっと意地悪なことを書いていきたいと思います。
【理論的思考の限界】
この本【美容室の開業】は美容室経営論であればメインの「ご飯」です。
これから僕が書くことは、この本の内容を理解したうえで魔改造する「おとなのふりかけ」みたいなものだと思ってください。
まず本題に入る前に、重ねて申し上げますが、この本は素晴らしい本です。批判したいわけではありません。
独立を考えている方は読むべき一冊です。
しかし、読んでいてふと気づきました。
「この本には独立に必要なすべてが書かれている。でも、もっと抽象的かつ複雑なことが経営現場ではあるよな」と。
もちろんこの本はこれから独立を考えている人のための本。
経営リスクを低減し、安定的な経営をするための基本的視点で書かれています。
とはいえ、この本の通りまんまやっても会社の爆発的な成長は望めないかもしれない。
この本に書かれている内容はいわば必修科目。より高い成長速度を望むのであれば、すべて頭に叩き込んだ上でプラスαが必要だと考えます。
例えば、この本の「クーポンサイトに頼らない美容室経営」の項目では、文脈から読み取るに、クーポンサイトを「頼るべきでないもの」と、暗に前提定義しています。
クーポンサイトを使わないで業績を伸ばせる美容室を目指すべきであるのはその通りです。
一方でクーポンサイトを使うことで、成長スピードを上げることができる。
これはエンジンみたいなもので、使うことでコストはかかるが、時間を買える。
リスクとリターンを考えることが経営の本質です。
現在の美容室市場における、クーポンサイトは善か悪か?の論調はただの二項対立ではありません。
一つだけわかっていることは
「善か?・悪か?」それは市場と顧客が決める。
ということだけです。
僕の違和感はここ。およそこの本には、通常の発想で考えうる正しいことがすべて網羅されているのですが、現在進行形のマーケット感覚に対し、理論的理想論に傾倒している部分があると感じる。
このことから思うのは「通常一般の経営セオリーに則って論理的に考えれば考えるほど、コモディティに陥る危険性があるのではないか?」ということ。
今日のブログの論旨はそのことについてです。
【セオリーに則って論理的に考えれば考えるほど、コモディティに陥る危険性がある】
「脱クーポンサイト」「ロイヤルカスタマーを掴め」「貸借対照表から経営を把握しろ」
論理的かつ理性的に意思決定できる組織能力を高めること。
これはセオリーであり、盤石な経営には必須条件です。
基本的な経営ノウハウがなければ、会社はあっという間に潰れます。
より優位性をもって市場で業績を伸ばすために論理的に考えるスキルが必要。
みんなそんなことは十分わかっている。
クーポンサイトに頼らない経営、年間12万円消費してくれるロイヤルカスタマーを獲得すること。自己資本比率を50%に引き上げること。
本書に書かれていることです。
論理的に考えている、なのにみんななかなか結果を出せない、伸ばせない。
これは考えてみれば非常に奇妙な状況です。
業績を伸ばすために論理化を進めた結果、皆が同じ戦場に集まって消耗線を戦い、それ自体がコモディティとなる。
いわば、論理化のコモディティ。
まるで囚人のジレンマのような状況に陥っているわけです。
さて、論理的なリソースを取り揃え、盤石な経営を目指したつもりが、それ自体がコモディティであるとした場合、次の勝つための戦略には何が必要でしょうか?
それは「スピード」と「コスト」です。
「スピード」
素早い意思決定と行動で他を出し抜くこと。
現在進行形のマーケティング課題にいち早く対応すること。
「コスト」
マイケルポーターが半世紀近く前に「競争の戦略」で述べたとおり、コストコントロールは競争優位性を作り出すための基本中の基本です。
無駄なコストは削り、他社に対して競争優位性を作ること。
さて、それでも全然足りないのが現代のビジネスフロンティアです。
みんなスピードは早いし、コストに対する戦略的意識もある。
みんな勉強してるし、情報を取得している。
それは企業も消費者も同じ。
しかし結果が出ない。
情報民主化が進んだ結果「論理化できる領域の多くが、すでにコモディティである」というジレンマを発生させている。
理論だけでは勝てない。
ここに問題がある。
【理論的思考のその先へ】
ここからが本題です。
まず単刀直入に。
僕が考えるに、世の中の「業績を伸ばせない」美容室経営(者)には大きく2種類ある
①理論的思考能力が高いけど美意識がない
②美意識が高いんだけど理論的思考ができない。
このどちらか。
①は理論化できているぶん、それなりに結果は出せますが、前述したとおりコモディティのど真ん中に突入していくことになる。
よほど優れたビジネスモデルでない限り、早期に成長の限界を迎える。
②はコンテンツ生成にセンスがあり、ブランドもある。しかし、ビジネスを論理化して捉えられていないので、ビジネスベースで事業を伸ばす発想自体思い浮かばない。
むしろ自分の世界観と合致しないものや、価値観を侵略するものに嫌悪を抱く傾向にある。
生意気で申し訳ないのですが、過去に僕が見てきた中では、うまくいってないケースは①・②どちらかの状況に当てはまります。
ではどうすれば差別化を図り、結果を残せるのか?
結論を述べると、結果を出せるのは①と②、良いとこどりのハイブリッドです。
「理論的思考ができ、美意識が高い」こと
ここに差別化の要諦があります。
美意識と書くとクソ意識の高いやつみたいで気持ち悪いのですが、便宜的に。
【美意識】をもう少しわかりやすくいうと「センス」とか「デザインやセオリーを別の角度から捉えらることのできる能力」と定義できるかもしれません。
もちろん僕やウチのサロンが「理論的思考ができ、美意識が高い」などと勘違いを掲げるつもりはありません。
ただ、少なくとも、他サロンと差別化を図るために意識的に努力してきたのは上記であることに間違いはありません。
【美意識は論理化できない】
通常「マネジメント・マーケティング。論理やフレームワークは真似できるけど【美意識】となると、どうすりゃいいの?」って話になる。
これはヘアデザインでも同じです。
経営でもヘアデザインでも、センスいい人は初めからセンスいいし、どんなに努力してもセンスがよくならない人もいる。
先天的な領域が多分に含まれる。
美意識は論理化できない。論理化できないものは伝達できない。
本を読んで「なるほど。こうしたら美意識が高まるのか」とはならない。
ここに理論的思考の限界がある。
ではどうすれば美意識を拡張できるのか?
おおよそ美意識を醸成するものは広義の「教養」です。
まずは哲学、文学、美術史などが近いでしょう。
しかし、普通の人は即効性のないこれらの領域を「明日からコツコツ勉強しよう」とはならない。
それよりも目の前に横たわっている諸問題を解決するための即効性のある実学を優先する。
むしろその方が判断としては正しいと言える。
上記の状況を逆手に取ると、不確定性、論理化、伝達できないもの。ここに差別化のヒントがある。
現代は【VUCA】の時代だと言われています。
V=Volatility(変動性・不安定さ)
U=Uncertainty(不確実性・不確定さ)
C=Complexity(複雑性)
A=Ambiguity(曖昧性・不明確さ)
不確実かつ不透明な先行きに対して、マーケティング、マネジメント、フレームワークなど、理論は地図となります。
しかし、全員が同じ宝の地図を持っているのであれば、それはすでに差別化にはなり得ません。
宝は分配され、すり減っていく。
新たな地図を獲得すること。それこそが「教養」またはそれから派生する美意識など、理論化できない領域です。
本来、哲学・文学など教養は大学で学ぶものです。
欧米の大学ではエリートはリベラルアーツ(教養)を学ぶ。
それは政治や経済など複雑性と不確実性の高い領域を扱うためにリベラルアーツが必要になるからです。
日本では必修でリベラルアーツを行っている教育機関は、東京大学とICU(国際基督教大学)だけです。(たしか)
そもそも僕も含め美容師は大学に行ってない人がほとんどですから、まずもってリベラルアーツの概念自体ないでしょう。
【どう不確定要素と向き合うか?~セルファウェアネス~】
さて。ではこれまで述べてきた「美意識」やら「教養」やらを、現場でどうマネジメントすれば結果を出せるのか?という課題が残ります。
哲学や文学や美術史を学ぶプログラムを社内で作ればいいのか?
いや、美容室の現場において、なかなかそんな悠長なことはやってられない。
やるべきことは、スタッフに教養を学んでもらうことではない。それはやりたい人がやればいい。
そうではなく「美意識や教養を使って経営者が会社やスタッフの能力を引き出す」ことです。
経営者は普段から読書なり多方面からの情報取得なり、学ぶことを続け、事業のパースペクティブ(局観)に対して美意識や教養のソースを組み込み、通常一般のセオリーを超えて会社を機能させるようにすること。
「セルファウェアネス」という言葉があります。
セルファウェアネスとは自分の状況認識のこと。
自分の強みや弱み、自分の価値観や思考性など、自分の内側にあるものに気づく力のことです。
スタンフォード・ビジネススクールでは教授陣が構成する評議会において「これからのビジネスリーダーの素養として、最も重要な要素は何か」というテーマで議論したところ、満場一致で「それはセルファウェアネスである」という結論に至ったそうです。
教養を養いセルファウェアネスの視点を獲得すると、自分の能力の客観的判断のみならず「人の能力の何が優れているのか」を判断できるようになります。
人の「才能」や「能力」というのは抽象的かつ論理化・数値化しにくい領域といえます。
その発見に繋がるのが、美意識であり、教養です。
僕は、自分自身がかつて受けてきた教育を鑑みた時に、今までの美容室における教育システムが、ポテンシャルを伸ばすのではなく、弱みを平均に引き上げる教育だと気づきました。
それがかつての常識であり、論理的セオリーだったのです。
ここに差別化要素があると考えました。
そこで会社全体の教育方針として、弱みはとりあえず置いておいて、強みにフォーカスを当てて伸ばす方法に切り替えた。
通常の理論的発想だと、それだと「教育やモラルがクラッシュする」と思うのが既定路線です。
また、自分の受けてきた教育が最善だという盲信もある。だからなかなか舵を切れない。
クラッシュを防ぐために必要なのが企業文化です。
SOCO/AO/SUNではそれを「自由と自律」という一文で明示しています。
文化を醸成することでクラッシュを防ぎ、理論のセオリーを超えて高い生産性と差別化を達成すること。
もちろん、そう簡単に達成できることはできない。
だから僕は伝わること、伝わらないことひっくるめ、自分の言葉や、今書いているブログでスタッフに伝えているわけです。
言葉を編み出すのは僕がかつて学んできた「教養」や「美意識」を元にしています。
自分の能力だけ伸ばしても会社全体の生産性は一向に伸びません。
コモディティの業界で突出して結果を出すということは従業員一人一人の能力を「通常とは違うやり方で」「爆発的に」伸ばすということ。
それは論理やセオリーから離れた視点でマネジメントを捉えないと達成できない。
「個人の才能」も「企業文化」も論理化できないし、そう簡単に真似できない。
この抽象性に対して解答を与えるのが、論理化・数値化できない能力を発見・開発できる教養や美意識の能力だと考えます。
【まとめ】
ここまで読んでくださりありがとうございます。
長くまとまらない文章をだらだらと書いてきてしまいました。
正月、本を読んだりネットフリックス観ながらこんなことをつらつらと考えていました。
明日から本年度最初の営業。
これからまた新しい戦いが始まるわけですが、僕は僕なりの戦いを続ける。
自分が正しい論考を述べているなどと思ってはいません。
そもそも正しい正しくない、善と悪、なんて概念自体、哲学的じゃないし教養に欠ける。
自ら捻り出した思考実験の証明をするのは自分自身というだけ。
教養を得る行為とは座学だけで達成されるものではありません。
様々な人との出会いや体験が自分の価値観を変化させる。
限界や制約を定めないこと。やれないことはない。
一年の計は元旦にあり。
自分の能力に挑戦するために今年も考え行動するのみ。
関山